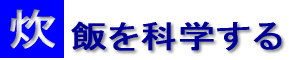
アンケート調査により「お米が美味しく炊けない」又は、「炊いてるつもりだけど正しくない」という人の割合が69%にも達しました。
米食味鑑定士・飯野陽夫が〝炊飯〟の家庭をチョット掘り下げて詳しく解説!
・レッスン1 計量
・レッスン2 お米を洗う
・レッスン3 浸漬
・レッスン4 水加減
・レッスン5 加熱
・レッスン6 蒸らし
・レッスン7 ほぐし・保温
・レッスン8 盛り付け
・レッスン9 食す
・炊き上がり診断
|
アンケート調査により「お米が美味しく炊けない」又は、「炊いてるつもりだけど正しくない」という人の割合が69%にも達しました。 ・レッスン1 計量 |
| lesson 1 計量 |
| お米の計量は正しく計るのが大原則! ●お米のカップは180ml 調理用カップは200ml 気づかずに使っている人、意外と多いんです! ★精米を1カップ多めにとり、カップの上部をすりきった場合 10回の平均重量⇒150g ★精米を1カップ多めにとり、カップの底を軽く揺すって平らにした場合 10回の平均重量⇒154g ★精米を多めにとり、カップの底を軽くたたいて平らにした場合 10回の平均重量⇒158g 雑になりがちな「お米の計量」分かっていただけたでしょうか?お米を美味しく炊くには大切なことなんですよ! |
| lesson 2 お米を洗う |
| 現在は精米機の進歩により、お米は研ぐというよりも軽く洗う程度で充分です。お米は力を加えて研いだ場合、〝軽く洗った〟時よりも洗い流される固形分や砕けまいが1%前後多くなってしまいます。また、お米の表面にも大きな違いが現れます。〝洗った〟ものは表面のデンプン細胞がデンプン粒で満たされていますが、〝研いだ〟ものは表面のデンプン粒の脱落が著しく細胞内はスカスカ状態です。もう一つ、お米を洗う場合、〝一回目の水は素早く流す〟ことはご存知ですね? どうしてかというと、〝洗米時の吸水はおよそ4割〟乾燥しているお米は水を加えると一気に吸水し始めます。洗米している3~4分間に浸漬水(炊飯前にお米に吸わせる水)の4割近くを吸水してしまいます。 1回目の水には、お米についているヌカ等が多く含まれています。この白く濁った水に含まれるヌカをなるべく吸わせないためです。 保温したお米が〝黄ばむ〟〝におう〟などの原因になることが多いようです。 |
| lesson3 浸漬(しんせき) |
| 炊飯する過程でとても大切なポイントです。 ★何のため? 硬い乾物であるお米には、1粒あたり15万個の部屋(デンプン細胞)があり、1部屋には200粒のデンプン粒が詰まっています。その内部にまで水を導くためです。そうすることで、加熱時の熱も内部に導き、芯のない、ふっくらしたご飯に炊き上げます。 また、水を吸収する際には、酵素を活性化させ、デンプンを柔らかくするためのエネルギーも発生します。さらに、健康なお米はこの間に不純物を排出します。 ★どこから? 水は胚芽の部分から吸収され、表面から吸水してゆき順次、内部へと吸水されていきます。だから、胚芽の残存率の高い〝胚芽米〟や〝○分搗き米〟〝玄米〟などは当然、浸漬時間も長くなります。 ★どんな水? 水の分子の固まりが(クラスター)が小さい〝軟水〟ほど浸透しやすく、酵素の活性を促し、より弾力のあるご飯にしてくれます。 電解水や浄化水、磁気水、ミネラルウォーターなら硬度40~60のミネラル分の少ない軟水がいいようです。 ★時間は? 水温が高ければ、吸水は早く、吸水量も多くなります。吸水量の70~80%は30分以内に吸水され、2時間で飽和状態に達します。 ※水タンクに備長炭や竹炭を入れておくと、カルキ臭を除去してくれて、水の分子も小さくなり遠赤外線効果でお米がふっくら炊き上がります! 最低でも30分。できれば1~2時間浸漬してください。このときの〝米粒〟の硬さは5/1~6/1位になっています。醤油や清酒を加える炊きこみご飯などは吸水が遅いので、30分位しか冷やさない場合には、ふっくら炊き上がらない場合があるかもしれません。2時間以上の浸漬時間があれば、ふっくら美味しく炊き上がります。 ★吸水量は? 15%前後だったお米の水分は、約30%になります。吸水量はお米の重さの20~25%、重量は約1.3倍に、膨張率は約1.25倍になります。 ※醤油だけの調味は風味は良くしてくれるんだけど、炊いているとき、泡立ちを抑え、蒸発量が少なくなってしまいます。だから、色が濃くなるだけでなく水っぽいご飯になってしまいます。だけど、清酒を加えることで風味を良くし、やや硬めでパラリとした食味のご飯にしてくれます。相性ばっちり!昔の人の知恵ってすごいですよね~ |
| lesson4 水加減 |
| 炊飯器のメモリはあくまでも目安として!水加減は ・ご飯の調理用途(普通のふつうのご飯か、すし飯にするか) ・嗜好(柔らかめ、硬め、どちらを好むか) ・米の産地や品種 ※品種はもちろん、同じ銘柄のお米でも栽培方法や栽培地によって水加減は違います ・米の新古(新米か古米か) ※同じ銘柄、産地でも、新米時と古くなったお米では水加減は違います。表示欄に複数年産と表示してあるものは、何年前のものかわかりませんが、水加減は多くなります。また、同じ年産のものでも、お米の保管状態によっても異なります。 ・炊飯器の種類 などを考慮する必要があります。 |
| lesson5 加熱 |
|
加熱はお米に最も大きな変化をもたらす工程です。現在は炊飯器のスイッチを入れるだけですが、お米はどのような過程を経て変化するのでしょう? |
| lesson6 蒸らし |
| 蒸らしとは、加熱終了後も、10~15分、蓋を開けずにそのままおくことです。ご飯粒が95℃にまで下がることを必要とします。この経過中に、ご飯の水分の移動があります。加熱終了直後(糊化度90.2%)のご飯粒は、糊化が不十分で周辺部が水っぽく、芯のあるような触感です。蒸らし終了時(糊化度93.9%)には、水分がご飯中心部に移動し、細胞の膨潤(ぼうじゅん)が進み、ご飯中心部まで糊化され、ふっくらとした触感のご飯になります。 |
| lesson7 ほぐし・保温 |
| 〝ほぐし〟とは、ご飯粒に冷気を当てて、表面を老化させて歯ごたえを作ることにあります。ほぐしのタイミングは、95℃~90℃です。ご飯が熱いうちにほぐしてあげてください。蒸らし時間が長くなり90℃以下になると、〝生戻り〟や、〝釜帰り〟といって、ご飯粒の周りにある遊離水が結露して表面澱粉が糊になり、密着してしまい触感の無い、ベチャっとしたご飯になってしまいます。ご飯は悪戯にこね回すのではなく、軽く、やさしく、素早くほぐしてください。 歯ごたえの良いご飯は、艶と透明感があります。 〝蒸らし〟〝ほぐし〟は炊飯のなかでもっとも大切な過程です。この作業をするか、しないかでは、ご飯の炊きあがりは雲泥の差。炊飯スイッチが切れたらすぐにほぐしましょう。 |
| lesson8 盛りつけ |
| 盛りつけは食べやすいように盛りましょう。2~3回に分け、少し山高に、ふんわりと、ご飯粒が立っていて、ほぐされていることがわかるように〝ふっくら〟盛りつけをします。 ちなみに、夫婦茶碗は大小、身体に合わせた合理的なサイズに思われます。お茶碗と汁碗は同じサイズで作られています。それぞれの大きさは男物(直径120mm)、女物(直径114mm)で、両手で作る円で等しく作られ、片手で横持ちし易く、安定な寸法につくられています。 |
| lesson9 食す |
| ご飯の美味しさを感じる温度帯は、47~48℃です。ご飯一口は20~30g。ほぐされていないご飯は固まり、口の中でもほぐれずにダンゴ状になってしまいます。炊飯直後は98℃、ご飯をほぐすと85~60℃、保温温度は55~60℃前後となります。食すとき、艶と甘味と香りと適度な粘りとこしがあるご飯が最高です。 |
| ★炊き上がり診断 |
| ・カニ穴がたくさんある ・ご飯独特の香りがする ・艶がある ・ご飯の釜離れがいい ・しゃもじが軽くご飯のなかに入る ・ご飯粒が大きく、、中心まで透明 ・食べてもホッコラとして、粘りがあり、水っぽくない ・いつまでも口の中に甘味が残っている ・ご飯の表面がしっかりしている 注意! ★炊飯量は、お釜の能力の6割くらいがベスト。多くても7割が限度です。 ★炊飯器のタコ足配線は禁物。特に冷蔵庫やエアコンなど、電気消費の多い家電とのタコ足は厳禁です。 お米アドバイザー・米食味鑑定士 飯野陽夫 |
| トップページはこちらです |